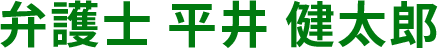東京地方裁判所医療集中部における事件概況等(令和6年)
2025.08.25お知らせ
法曹時報77巻7号では東京地裁医療部における令和6年1月1日から令和6年12月31日までの医療事件第一審の概況等がまとめられている。
統計的なデータ及びそれに対する評価は以下のとおりです。
新受件数 136件(全国658件)
平均審理期間 17.2月(全国24.9月)
※東京地裁の審理期間が全国に比べて短く、かつ前年より短くなっていることから、審理の迅速化が進んでいることがわかる
診療科目(新受件数のうち) 内科29件(21.3%)、歯科(含口腔外科)24件(17.6%)、形成外科(含美容)15件(11.0%)、外科14件(10.3%)、整形外科13件(9.6%)
※昨年看護・介護上の過失が整形外科よりも多かったが、本年は整形外科の方が多く、一昨年以前の傾向に戻ったと思われる。
・内科の内訳は消化器7件、循環器6件、呼吸器4件、脳神経2件、その他10件 ※昨年と比較して内訳に変動はなかった
・外科の内訳は消化器6件、循環器4件、脳神経2件、呼吸器0件、その他2件 ※昨年と比較して循環器と脳神経の件数が逆転した
事件の終局 判決率44.3%(昨年より増加)、和解率50.0%(昨年より減少)
・若干のばらつきはあるものの、概ね理期間が長い事件ほど判決率が高くなる傾向にある
・令和6年に成立した和解70件のうち、尋問前に成立59件(84.3%)、尋問後に成立10件(14.3%)、鑑定後に成立1件(1.4%)
・尋問前の和解が多いのは、①診療録や医学文献から診療経過や医学的知見を客観的に認定し、確度の高い心証を形成でき、②医療従事者の尋問を回避する意向などが理由として挙げられている。
※尋問前の和解が多い理由は昨年と同様の記載であるが、東京地裁が積極的に尋問前に心証形成・心証開示を行っていると思われ、その結果が尋問前和解の増加に繋がっていると考える
※尋問前の和解の増加が審理期間の短縮にも繋がっていると考えられる
(一部)認容率 24.2%(全国17.5%)
判決に対する上訴の比率 57.6%
和解の内訳 請求額の20%未満の金額での和解が全体の58.6%を占め、請求額と比較して低額での和解が多い傾向が見られる(以前と変わりなし)
・和解によって終局した事件の中には、裁判所が医療機関側に賠償責任があるという心証を抱いた事件が一定数存在し、その多くが判決ではなく和解によって終局しているため、判決における認容率及び認容額が少なくなっているものと考えられる
・約7割が棄却判決であって、認容判決であっても医療機関側に1000万円を超える高額な賠償責任を認めるものは少ない。
※和解であっても請求額の20%未満の金額での和解が約6割であり、患者側にとって訴訟がいかに厳しい戦いであるかがわかる
統計的データ以外については以下の指摘があった。
①医学的知見の獲得
・代理人弁護士(特に患者側代理人)が医療事件に不慣れなため、医学的知見の獲得に難渋し、主張が明確化されるまでに時間を要することがあり、争点整理が長期化することもある。
②協力医の意見書
・令和6年は既済事件140件のうち54件(38.6%)で意見書が提出されている。 ※昨年と割合は変わっていない
・意見書を作成する時期としては、争点整理の中盤から終盤が一般的である。
・既済事件140件のうち37件で尋問が実施され、うち協力医の尋問が実施されたのは9件である。
これらは裁判手続に進んだ場合のデータです。
ご依頼いただいた事件全てが裁判手続に進むわけではなく、示談交渉によって話し合いで解決する事件も多くあります。
裁判手続に進む場合には、こういったデータを踏まえて、どれだけの期間や費用がかかるのか、といったことを説明させていただいています。