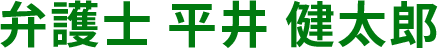【医療過誤裁判例】精神科病院で身体的拘束を受けた患者が肺血栓塞栓症によって死亡した事案
2020.11.25お知らせ
精神科病院で身体的拘束を受けた患者が肺血栓塞栓症によって死亡した事案(金沢地裁令和2年1月31日判決、判例時報2455号)の備忘録です。
この事案では、身体的拘束の違法性、肺血栓塞栓症の予防措置をすべき注意義務、死亡との間の因果関係が主な争点です。
1.身体的拘束の違法性
身体的拘束については「厚生労働大臣が精神保健福祉法37条1項の委任を受けて精神科病院の管理者が遵守すべき基準として定めた告示第130号」があることを前提に、「身体的拘束も医療行為又は保護行為の1つとして行われるものであり、「多動」「不穏」等も評価を含む概念である以上、同要件の判断において、専門的知見を有する指定医に裁量がないということはできず、指定医が必要と認めて実施した身体的拘束が違法となるかの判断においては、指定医がアないしウの場合又はこれに準じる場合であって身体的拘束以外によい代替方法がないと判断したことに裁量の濫用又は逸脱があったかどうかを検討することが相当である」と判断基準を設定しています。
なお、「アないしウ」とは、「主として」「ア 自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合」「イ 多動又は不穏が顕著な場合」のほか「ウ 精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合」のことです。
判決では、この判断基準に従って、具体的経過をもとに身体的拘束が違法であるとはいえないと判断しています。
2.肺血栓塞栓症の予防措置をすべき注意義務
「静脈血栓塞栓症予防指針-日本総合病院精神医学会治療指針2」(学会指針)を基礎資料として、患者の「総合的なリスクレベルは、少なくとも学会指針にいう「中リスク」には該当したと認められる」とし、「学会指針が推奨する「低リスク」又は「中リスク」の予防法(⑤早期離床及び積極的運動の心がけ、⑥弾性ストッキングの装着、⑦間欠的空気圧迫法)のうち、被告病院においても当時容易に実施可能であった予防措置については、これを実施することが当時の医療水準として求められていたというべきである」と判断しています。
判決では「本件身体的拘束期間中、弾性ストッキングを装着すべき注意義務を負っていたと認められ」「本件身体的拘束の際、弾性ストッキングを装着していなかったから、被告には、上記の注意義務違反が認められる」と病院の過失を認めました。
3.死亡との間の因果関係
判決では以下のように述べ、因果関係を否定しています。
「弾性ストッキングの装着については、前記のとおり学会指針が推奨する予防法であるほか、証拠上、「中リスクの患者では有意な予防効果を認める」、「中等度のリスクを有する手術後の患者では静脈血栓塞栓症の有意な減少を認めている」などとされており、少なくとも中リスクに該当する亡Aにとっては有効な予防措置であったと認められる。しかしながら、学会指針は「本ガイドラインであげたリスクのみでは静脈血栓塞栓症の完全な予防は困難であることを念頭に置く必要がある」とし、松沢報告も「静脈血栓塞栓症には安全かつ100%予防可能な方法はない」としていること、弾性ストッキングを装着した場合でも患者が死亡した事例が多数存在すること、身体的拘束自体のリスクレベルが低くないと考えられていることを総合すると、亡Aに12月14日から弾性ストッキングを装着していたとしても、同月20日に亡Aが急性肺血栓塞栓症により死亡することを確実に回避することができたと認めることはできない。」と述べ、高度の蓋然性(因果関係)は認められませんでした。
判決の最後の結論部分では、最高裁判所の判決を意識した判示にはなっているものの、理由を述べるところでは「死亡することを確実に回避」という言葉遣いがされています。
この「確実に回避」という用語からすると自然科学的に100%の因果関係を求めているようにも読めます。松沢報告の「100%予防可能な方法はない」を敢えて引用していることからも「高度の蓋然性」ではなく、「確実」100%を意識しているように思われます。
実際のところは不明ですが、「確実に回避」というのが100%かそれに近いものを意識しているのであれば、患者側としては証明が極めて困難になります。
また、本件では「相当程度の可能性」については判断がされていませんが、他の肺血栓塞栓症に関する裁判例では「相当程度の可能性」が認められた事案もあります(東京地裁平成23年12月9日判決、判例タイムズ1412号)。